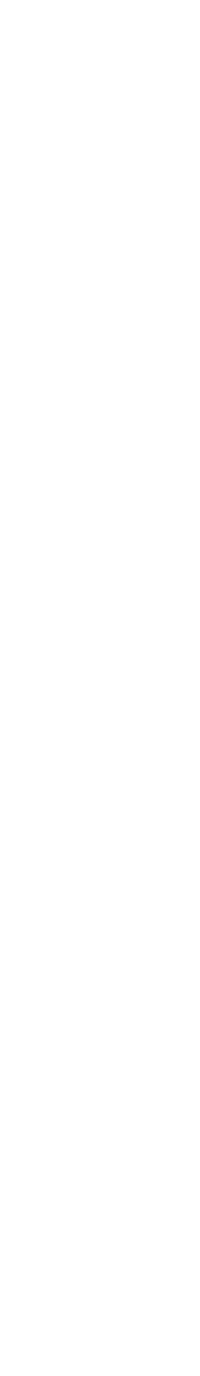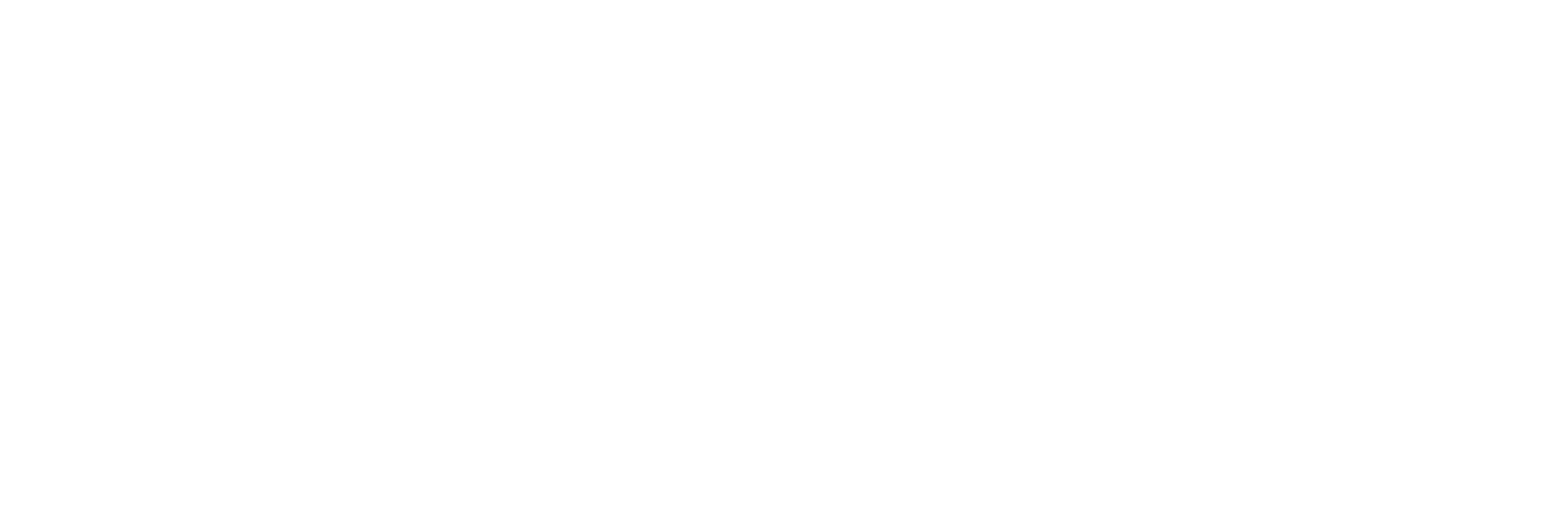「あしたの郊外」は国土交通省の方から、郊外で増える空き家に対するモデル事業に取り組まないかと声をかけていただいたことがきっかけで、立ち上げることになりました。
取手には、東京芸術大学のキャンパスがあることもきっかけになって、多くのアーティストが生活しています。このまちだからこそできる空き家の使い方を考えていくなかで、建築家に限らずアーティストや市民まで、アイディアを広く募集するプラットフォームとして立ち上げたのが、Webサイト「あしたの郊外」でした。
プロジェクトの名前を考えているときに、馬場さんが「あしたの郊外」という言葉を投げかけてくれて。僕たちは郊外に責任があるから、プロジェクトに希望を託したいんだっていう話をしてくださって。郊外が社会の変化とともにつくられたと考えたときに、すごく納得したんです。
一方で20代のメンバーが「あしたの郊外」という言葉に対して、「夕暮れみたいで、悲しい感じがする」と言ったことにも共感できて。私もどちらかというと郊外が原風景、育ってきた景色がそもそも郊外なんです。だからネガティブに捉えているわけではないんですよね。世代によって郊外への認識が違うことが、プロジェクトを進めていくなかで浮き彫りになっていたのはよく覚えています。
2015年に開催した「あしたの郊外 キックオフ・シンポジウム」では、「郊外を考える人」としてプロジェクトに参画していただいたBank ARTの池田さん、スローレーベルの栗栖さん、アーティストの【目】がそれぞれの視点から郊外について話をしたり、郊外に広がる空き家を活用するアイディアを発表してくれました。それを求心力として寄せられた94のアイディアを、すべてWEB上で公開していったんです。
実現する保証もないなかでアイディアを好き勝手に出す。ポジティブでもネガティブでもどっちでもよくて、郊外について自由に議論する。
個人的には、その様子を“はらっぱ的”だと感じていて。2005年に、駅前の丘の上にあった、空き地を使って実施したプロジェクトと重なったんです。私たちはその空き地を「はらっぱ」と呼ぶことにしました。まずは空き地に登るための階段をつけるところからはじめる。なんでもない場所に階段がついたら、なんだろうって思うでしょう。はらっぱって、遊び方が決まってないですよね。
そのうちに子どもが登ってきて秘密基地にしたり、おっちゃんがブランコをつくったり。やりたいことを各々発表してみたりとか。鬼ごっこやかくれんぼでも、ぼんやり昼寝していてもいい。そのはらっぱでは、誰がなにを考えてやっても、それぞれが同じ場所に居合わせることができた。

アーティストの力を借りてはいるんですけど、みんながのびのび、やりたいことを重ねたような場所になったんです。いろんな人が来て、自分のやりたいことを見つけて、好きなように実現できる包容力がある。郊外をそういう場所にしたい、取手もまち全体がはらっぱ的になったらいいんじゃないかっていうのが個人的に思っていることです。
自分のなかで郊外は、あまり固まりきっていないイメージがあります。だからこそ、いろんな人の余力が花開くような場所になるといいと考えていて。今、取手アートプロジェクトがやっていることもすべて、アーティスト、市民、スタッフ問わず関わる人たちの多様な発露に支えられている。そういった取り組みが、今後の社会で生きにくい人が徐々にでも少なくなるような価値観とか、ものの捉え方を広げるためのエンジンになるといいなと思っています。