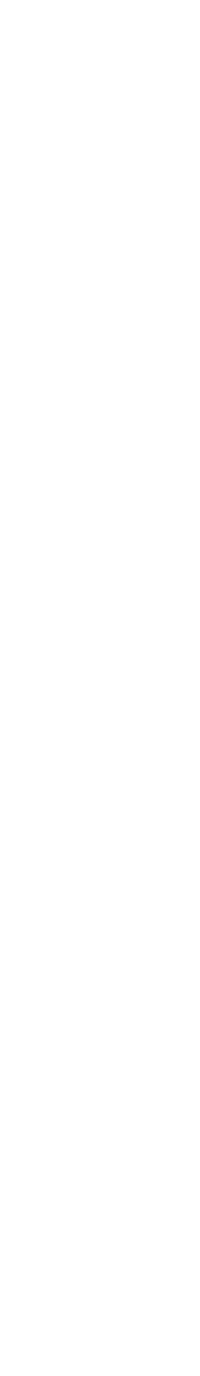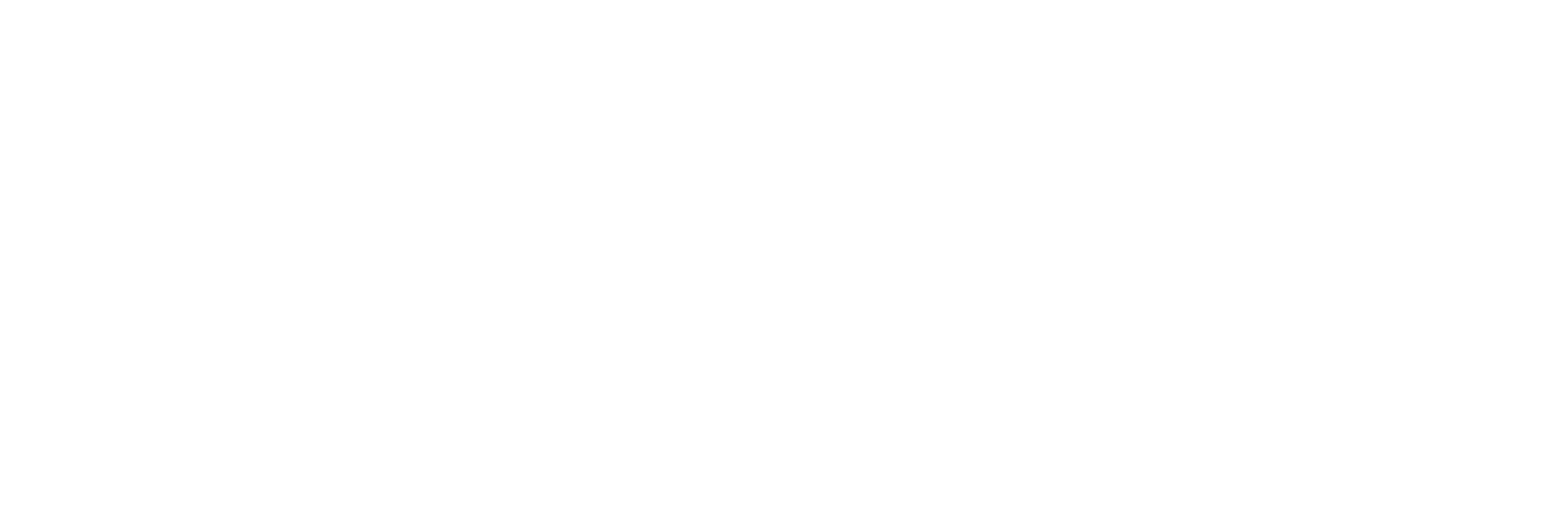1「郊外」になった地方都市
熊倉:取手アートプロジェクト(以下TAP)は1999年〜2009年まで、会期を設けたフェスティバル方式で開催していました。全国から選ばれた作品を見せる展覧会の年と、住んでいるアーティストたちのオープンスタジオの年を交互に開催していたんです。その頃は、芸大教授の渡辺好明さんが中心になってやっていらしたんです。
私自身は2002年、芸大の取手キャンパスに音楽環境創造科ができた時に助教授に就任しました。そうしたら渡辺さんからすぐにメールが来て、引きずり込まれるように(笑)2003年からTAPに関わるようになりました。その頃のTAPは人手も足りなくて、先端芸術表現科も手を引いたりして、ちょうど盛り下がっていた時だったんです。それで、アートプロジェクトのマネージャーを育成する「TAP塾」を始めました。
ところが2009年、渡辺さんが亡くなったのをきっかけにTAPが存続の危機に陥って、それまでのフェスティバル型を見直すことにしました。ちょうど越後妻有など里山型の芸術祭と、横浜トリエンナーレのような都市型の芸術祭が増えてきていたので、そのどちらとも違う形にしようと。郊外都市である取手は、農村都市でもあり住宅街でもある。そこで住宅地という側に焦点を当てた「アートのある団地」、自然や農業の事を考える「半農半芸」という2つのテーマを立てました。作品をつくらないわけではないですが、会期を設けて展示をする、という形式はやめたんです。
住友:でも、絶えず何かが起こっている。
熊倉:そうですね、小さな拠点をつくったり。「半農半芸」では畑を借りて綿花を作ったり、染織家さんが自然素材をつかって絵の具を作ったり。2010年からは、雨漏りする農協の古いビルを改装してTAPの拠点にしています。そこに6組のレギュラー・アーティストがいたり、取手はアーティストがたくさん住んでいるので、その人たちと展覧会やワークショップをやる、という活動がひとつの柱です。
「アートのある団地」では、井野団地のもうあまりお店の開いていないショッピングセンターに『いこいーの+Tappino』というコミュニティカフェをつくってアートのワークショップなどをやっています。もうひとつの戸頭団地では何十年かに一度の壁面の塗り直しに合わせて、アーティストの上原耕生さんが壁画を描いている『IN MY GARDEN』という作品もあります。ここは70年台の理想の都市計画としてつくられた団地ですが、移り住んできた人たちが今ではもう高齢化していて、空室が多くなってきています。。
そんなことをしていたら、国土交通省から郊外の空き家問題に取り組む事業を募集していると聞きまして、Open A馬場さんと応募してみたんです。流通促進の管理業者、ディベロッパー、不動産業者といった事業者の中で、アートの分野で採択されたのはTAPだけなのですが、空き家住宅問題を考えるプロジェクトとして「あしたの郊外」を立ち上げました。貸せない物件や貸す気がない大家さんの物件を掘り起こして、アーティストが作品化する「取手アート不動産」という活動もやっています。
「目」の南川さん・荒神さんには、このプロジェクトに「郊外を考える人」として加わっていただいています。お二人は私が埼玉県の北本市でプロジェクトをやっていた時にレジデント・アーティストとして住んで頂いたご縁です。今でも北本に住んでいて、すごい活気のあるファクトリーを持っていらっしゃるんですよね。そして住友さんはアーツ前橋の館長として、今回『ここに棲む』という展覧会を企画されて。現代美術の文化施設で、地域のことをテーマにするのは珍しいですよね。
住友:僕としては素直に「こういうのが今のアートには必要だろう」と思ってやったのですが、そういう反応をたくさんいただきますね。
熊倉:「美術館が、うちのまちのことなんか考えてくれるんだ」って。
住友:「ここに棲む」展のオープニングで前橋市長が「そうか、現代美術は社会のことも考えられるんだね」と。前橋も「都心ではない」という広い意味では、たしかに郊外ですね。でも、そもそも価値観が変わっちゃっている。「大都市には何でもある」とは、みんな思わなくなっちゃってるわけだから。
熊倉:東京の人にとって「地方に住む」と聞くと“田園の中に住む”というイメージがあるかもしれませんが、交通が発達した結果、地方都市が「郊外」のような場所になってきている。
前橋にも空き家がたくさんあると思います。アーツ前橋は「美術館」であるにもかかわらず、街の中でもいろいろと企画をされていますよね。
住友:僕らはもともと開館前から活動していて、その時は建物がないから、空き家でアーティスト・イン・レジデンスをやったりしていました。ただ必要性からやっていたことでしたが、それなりに地域の方たちから反応があって、「開館したらやめる」という選択肢もあったのですが、やめられなくなった(笑)。ただ美術館の運営って結構大変なんです。芸術祭とは仕組みも違う。展覧会は3ヶ月で終わってアーティストも帰っちゃうけど、「地域」って終わらないじゃないですか。そこが大きな違いだと思う。開館前からやってきたことを、どうやって持続させていくか。そのコーディネートを可能にする仕組みを、いま市役所や、地域でまちづくりに関心のある若い人たちと議論しているところです。
美術館のあり方としてはいろいろな形があっていいと思いますが、うちの場合にはアーティストが場所を持つことが、重要だと思ってるんです。抽象的な意味でも、アトリエという意味でも。ここには、何十年も前からしぶとく場所を維持されてきた地元の作家さんたちがいて、そういう人たちと一緒に何かをやっていくことが、新しい美術館として大切なことだと思いました。美術館って、みんな「突然できた」と思うんですよ。でも本当は、もともと文化があるところだからこそ美術館ができる。東京の流行がどうであろうと脈々と「場を持つ」ということをやってきた人たちがいて、その流れを引き継ぎたいなと思った時に、アーツ前橋としては「街の中でやる」という選択肢がいいと思ったんです。
熊倉:今回の展覧会『ここに棲む』は、どういう経緯で生まれたんですか?
住友:去年の秋に服飾の展覧会をやったんです。前橋は戦前まで生糸の輸出で栄えた街です。そこで「服飾=衣」から初めて「住」「食」へ、日常生活という切り口で企画した三回シリーズの第二弾です。一緒に企画をさせていただいた前橋工科大学の石田敏明さんは若いころ伊東豊雄事務所にいた方です。建築家は社会を俯瞰的に見るじゃないですか。だから個人の感性で物をつくる美術作家も入った方がいいなと思って、7人の建築家と7人の作家で構成しました。
熊倉:7人それぞれ、ずいぶん違いますよね?
住友:全然、違います。たとえば藤野高志/生物建築舎は自然のもの・有機的なものと人工的なもの=建築のあいだに境界線を作らないという考え方を持っている。彼の展示の中で、置物のクマの体内にリビングルームがあったと思います。人間や動物の身体はエアコンなんかなくても自動で体温調節するじゃないですか。だから一番環境維持性能がいい、というラディカルな発想。あり得ないことなんですが、あり得ないことを考えるのが芸術だから。彼なんかは建築家というよりアーティストに近いんです。
一方でアトリエ・ワンとかツバメアーキテクツが提案しようとしている、福祉や高齢化に対するソリューションは、大手ゼネコンなんかができない部分ですよね。今まさに、みんながどうしていいかわからないことを、本当に手探りでやろうとしているんです。