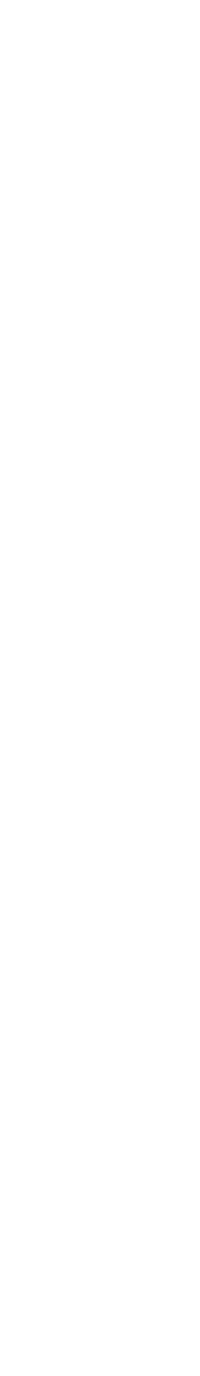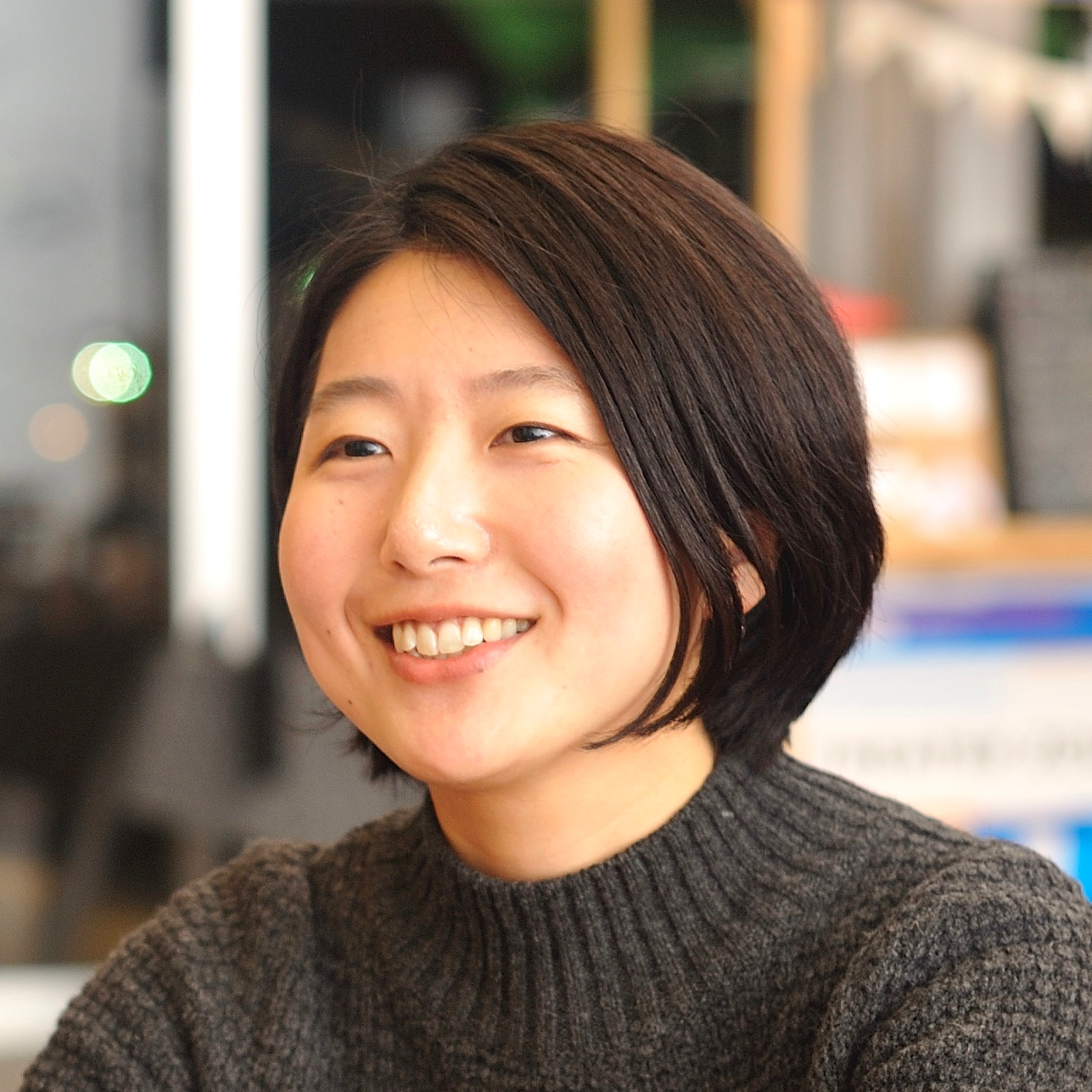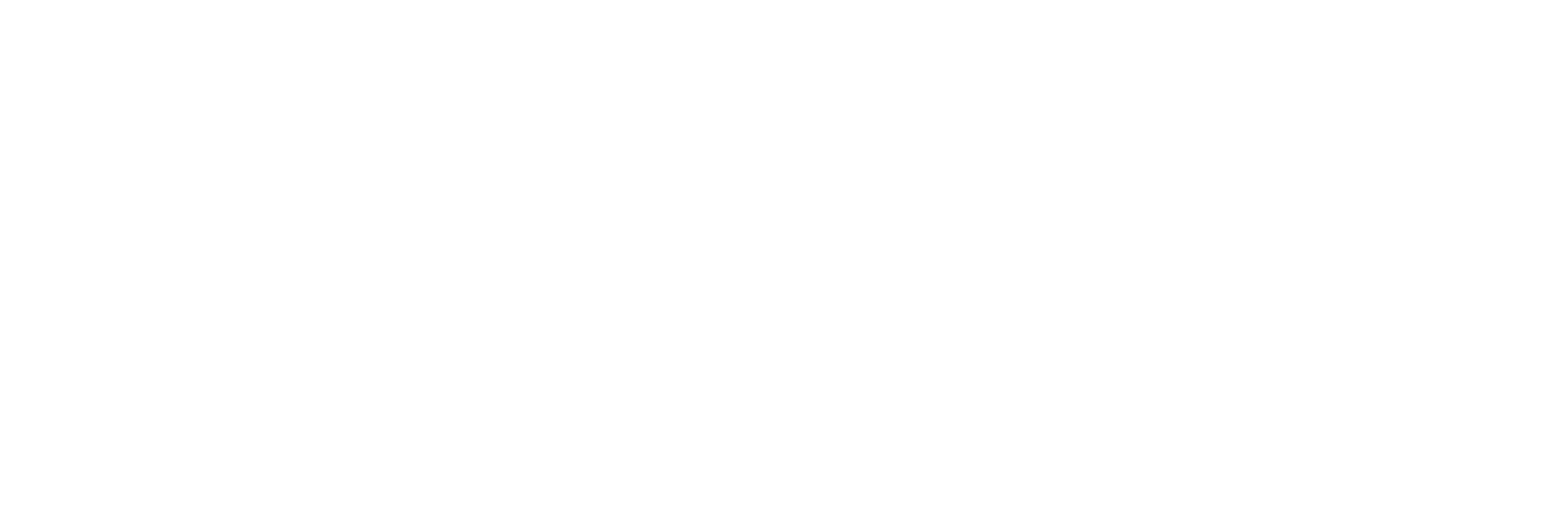13年かけて、100人に届くこと
栗栖:石神さんの事務所はこのあたり(「象の鼻テラス」のある横浜市中区の港湾エリア)なんですよね。
石神:2015年9月まで馬車道にいました。今度は伊勢佐木町に拠点をつくろうと計画中です。
森:地方だけじゃなく、横浜でも企画をやっているんだよね。
石神:はい。2015年は緑区で開催されたスマートイルミネーションみどりと、本牧アートプロジェクトの2つに参加しました。どちらも、横浜の郊外エリアですね。
森:本牧でやった『ギブ・ミー・チョコレート!』(2015年12月)はどんな作品だったの?
石神:本牧のまちの人たちで秘密結社をつくる、という企画です。口コミだけでメンバーを増やして、3週間くらいで30名弱の人が集まりました。そのメンバーたちがそれぞれ、まるで普段通りに暮らしているかのように、まちに紛れ込んでいる。家や職場だったり、よく行く場所だったり、自分の生活や記憶に関係のある場所にいる。作品を体験する参加者は、指示書をもとにメンバーを探してチョコを受け取るというルールです。チョコを受け取るために必要な合言葉や手続きは、一人ひとり違います。3人のメンバーに会うと「楽園」と呼ばれる場所への行き方を教えてもらえる。「楽園」は地元の常連さんだけが集まる秘密の場所で、結社メンバーたちの個人的なエピソードが集められた本を読むことができます。
森:なぜチョコだったの?
石神:本牧はもともと米軍に接収されていた土地で、今回の結社メンバーの中には、実際に子どものころ「ギブ・ミー・チョコレート」と言っていた70代の方もいます。楽しい思い出として記憶している人もいるし、本牧の負の歴史でもある。一方で、返還後に開発されたニュータウンに入ってきた新住民の人もいるし、返還前後の空気を知らずに育った中学生くらいの子もいる。そういういろいろな層の人たちが、歴史に押し付けられた言葉を逆手に取って、自分たちでその言葉を使って遊ぶことをしたかった。個人的には、口コミでメンバーが増えていく過程や、自分で場所を交渉して見つけてくるメンバーがいたり、私が言っていない演出を勝手にやってくれている人がいたりしたのも面白かったですね。
森:これは演劇なの?
石神:はい。参加者には最初に「これは、あなたとメンバーとの共犯関係で上演する演劇である。一期一会を味わうこと」と伝えています。参加者とメンバーの間であらかじめ決められた手続きをしないといけないんですけど、「周囲にさとられてはいけない」というルールがあって、ミッション通りにやらないとメンバーは答えてくれないし、チョコももらえない。
森:参加者は何人でもいいの?
石神:メンバーは日替わりですが、同時多発的に3人×6コースが起動していて、18人のメンバーがまちに潜伏していました。参加できる人数は一回最大50~60人で、2日間開催しました。
森:じゃあ100人だね。「百人」という単位は面白くて。そういうマイクロな単位ってすごくいいと思うんだけど、それより大きいのはつくる気がないのかな。
石神:そうですね。自分で全員に会いに行くから現実的にそういう規模感になる、という面も大きいですけど。
森:栗栖さんは「一万人」の方でしょ?
栗栖:私は無限に増やしたい方ですね。なるべく大勢の人。でも今は、場面によって人数を絞ることもできる。二人、三人、と増えていくパターンだから、自分が接する人数には限界があります。でも、どんどん巻き込みますね。
森:企画をやっているのは、自分が親しんでいるまちなのかな。
石神:本牧に関わり始めて今回が3年目だったんですけど、キーマンがどこにいるかとか、人のつながり方とか、3年いたから見えてきたところは大きかったですね。
栗栖:私も住民を巻き込む作品の時は、3カ年計画です。最初の年は友達をつくったり、まちを下調べするところから入って、2年目に何となく計画を立てて、3年目に実行。知らないまちでやるときは、だいたいそのくらいのスピード感でやらないとうまくいかない。
森:その時間は、かかっているの?かけているの?
栗栖:かかっちゃう。急ぐとやっぱり、やれることに限界がありますよね。
森:でも、それ(3年かかること)がわからない人と仕事しなきゃいけないこともあるよね。そういう時はどういう風にしているの?巻き込むか、諦めるか。
栗栖:私にミッションを与える立場のクライアントには「3年かかる」ということをわかってほしい。でもそれ以外の人とは、それこそ一期一会の出会いを繰り返しながら仲間になっていくので、必ずしも全員にとって3年かかるというわけではないですね。
森:その「3年計画」をチームの中で共有できていると、共犯関係ができるじゃないですか。コアになる人と共有はしているの?
栗栖:いや、3年かかるとは言っていないですね。自分の中では、だいたい3年くらいの構想を立てますけど、周りの人は目の前のことをこなすことで精一杯だから。
石神:私の場合、もちろん劇団のメンバーは理解しているし、そういう創作環境をつくろうとしています。ただ地域のパートナーとはすり合わせが必要ですし、場合によっては「今おっしゃっていることは、今年はできないと思います」という話をすることはあります。
森:地域の人は、早く成果がほしいわけね。
石神:早くというか、地元で動いてくれる人たちは地域内の立場や周りとの関係性もあるので「自分たちも協力したいけど、このくらいの成果を出さないと周りに理解してもらえない」というプレッシャーがかかることもあります。最初は何も期待されていなかったのに、後から助成や支援がついてきて周りからの期待が高まってくると、立場的に私たちよりも焦らされてしまう、というのはあると思います。