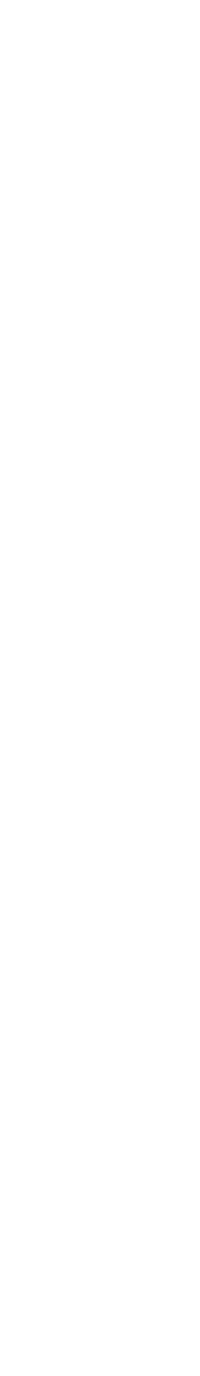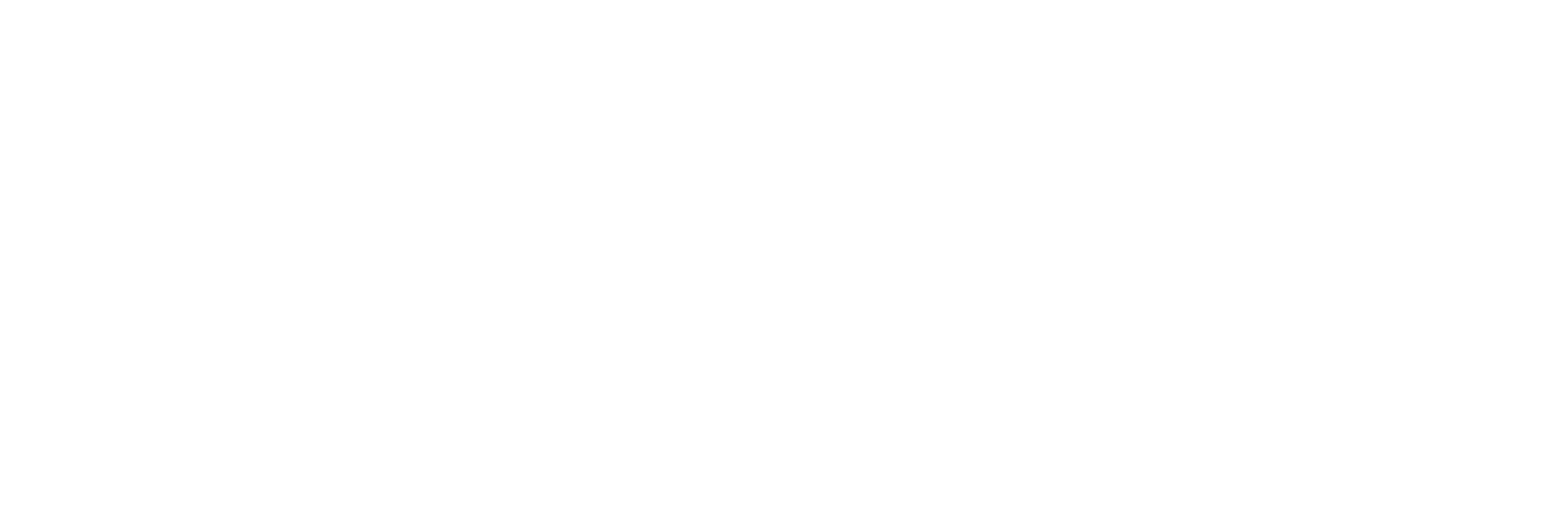1取手を通して、郊外のアイデンティティを考える
馬場:僕が取手アートプロジェクト(以下、TAP)に関わるようになった 3 年くらい前というのは、TAP がちょうど大きな転機を迎えていた頃だったと思います。TAP が始まった当時は、もともと東京芸大あったこともあり、さまざまな場所に作品が展示される華やかなアートイベント、という様相が強かった。
ところが時は流れ、今や全国各地でアートイベント花盛りという状況です。その中でかなり早い段階から活動していた TAP は、団地で事務所を構えるなど、自分たちが立脚している場所をベースに、以前とは少し違うスタンスでアートを考えようとし始めた。
そんな中で作品というモノを展示するのではなく、一泊二日で来たアノニマスなお客さんを、団地の住人たちがホテルマンを演じながらもてなすドラマをアートとして提示する『サンセルフホテル』といった作品が生まれてきた。僕としては「これを果たしてアートと呼んでいいのだろうか」と思うくらい、形がなくて、偶然性にあふれた作品です。その様子を見ながら、アートの位相がずいぶん変わってきたのではないか、と思い始めました。
つまり、この取手という郊外でアートプロジェクトをやる意味、やることのアイデンティティを考え始めたのが「あしたの郊外」のきっかけです。瀬戸内国際芸術祭のような地方都市で、圧倒的な風景、圧倒的な人口減や過疎といった状況のなかで行われるアートプロジェクトは、ある種のフォーマットが見えてきています。一方、札幌や名古屋では、都市のすきまでアートがどういうふうに振る舞うか、都市的な文脈とアートの文脈がどう距離感を持つかというところで語られている。では、この都会でも田舎でもない、ドラマティックな風景があるわけでもない、人口がたくさんいるわけでもない、ベッドタウンと呼ばれる郊外でアートが果たす役割とは何なのか、果たして存在意義はあるのか。
昔は都市政策によって、過密する中心を避けるために郊外というものを量産してベッドタウンと名づけた。でも今は高齢化や過疎も進み、郊外に住む人は減る一方で都心居住は進んでいて、郊外に住む目的はどんどん薄れている。
一方で僕は郊外育ちだから、原風景として懐かしくもあるんです。ただ今の若い世代にとっては必ずしもそうではない。今後、郊外というものがどうなっていくのか、朽ちていくのか滅びていくのか、それとも違うアイデンティティを獲得するのか。僕は建築や都市計画のフィールドから、それをずっと考えてきました。
ただ、なかなか確かな解答が見つからなかった時に、アートという、僕から見ると少しつかみにくい概念を通して、「郊外」を考えるプロジェクトにできないかと考えた。そこで「あしたの郊外」という言葉を立てて、池田さんやアーティストの「目」、あるいはアート・プロデューサーの栗栖さんといった、背景も世代もバラバラの人たちと一緒に語り始めたところです。
池田:TAP はもともと、東京芸大というある種、非常に特別な学校周辺のアートプロジェクトという様相を強く帯びていました。それが「郊外」という、より一般的で大きな問いに向かった。僕個人としては「果たしてその問題の設定の仕方はどうだろう」と思いながら見ていることは確かですね。郊外は、別に取手でなくてもいっぱいあるわけだし。それが問題をわかりにくくしている部分もあると思う。
若林:「郊外」という問いと、取手で何かやっていこうというのは、重なるところもあるけれど、ずれていく部分もあるじゃないですか。でも取手を通して、郊外について見えてくる部分というものもあると思う。相互に触発しあうような対話があれば、きっと面白いだろうな、と思いますけどね。
馬場:池田さんには開口一番、「郊外って年金問題くらいでかい問題だぞ」と言われたのをよく憶えているんです。でも、郊外とアートについて語るものはこれまであまりなかったから、いい機会だなと。取手という場所性ならではの、サイトスペシフィックな解答もあっていいし、もっと一般的な解答もあって、それらが混在していていい。
池田:今回は国交省の助成事業のアート部門という印象を受けたんですけど、それは合っていますか?
馬場:「あしたの郊外」と「取手アート不動産」は、国土交通省の空き家対策事業の助成対象プロジェクトになっていて、全国の20都市くらいで福祉や教育といったテーマの取り組みが並んでいる中に唯一、アートというすごく珍しい切り口で入っています。
池田:北川フラムさんがやってきた『越後妻有アートトリエンナーレ』も実を言えば、里山をつくるという言い方で、市町村合併を推進するプロジェクトが始まりだったんですよ。もともと妻有は市町村だったけれど、今は十日町市と津南町だけですからね。
馬場:平成の大合併とリンクしているんですね。
池田:国は相当焦っていますからね。里山、高齢化した農村、それから団地、年金といった問題が起きて、何百万人というレベルでおかしくなってきている。それを何とかしなければいけない、という構造ですよね。